

スマホdeほけん編集部監修者
ファイナンシャルプランナー
保有資格
AFP・2級FP技能士
専門分野・得意分野
生命保険・社会保障・金融全般に精通。保険業界での実務経験をもとに、ユーザー目線で正確かつ中立的な情報発信を行っています。
「終身保険でも教育資金を準備できる?」と迷う方へ。返戻金や死亡保障、家計インパクトを踏まえ、学資保険との違いを整理します。
本記事は、返戻率の考え方から設計手順、デメリット対策までを網羅。迷わない判断軸を提示し、老後資金と資産形成の両立も解説します。
結論と基本|終身保険は代替になり得るが設計次第で差が出る
終身保険は解約返戻金を教育費に充てられるため、学資保険の代替になり得ます。低解約返戻金型なら払込満了後の返戻率が上がりやすいのが特色です。
一方で、解約時期や設計を誤ると元本割れも起こり得ます。家計との整合と受取タイミングの調整が重要です。
まずは「何を優先するか」を数式レベルで固めましょう。以下のチェックポイントから手順通りに進めると迷いません。
各項目の詳細は見出し下のh3で深掘りします。リンクの順番通りに読み進めれば、判断の土台が完成します。
1. 目標額と受取時期の確定
高校・大学などの学費カーブを年次で可視化し、必要額と時期を決めます。臨時費用のバッファも2〜3割見込みましょう。
受取時期=解約時期のため、学資より柔軟ですが計画性が不可欠です。
2. 入金計画と返戻率の試算
月払い・年払いの合計と返戻率を比較します。払込満了後の返戻率が100%超になる時点を把握しましょう。
家計の季節変動に合わせ、無理のないキャッシュフローに設計します。
3. 終身か学資かの一次判定
死亡保障の要否、受取の柔軟性、返戻率の水準で比較します。教育費専用なら学資、汎用性重視なら終身が有力です。
迷う場合は併用でリスク分散。目的の重複は避けます。
4. 低解約返戻金型・払込期間の最適化
払込中は返戻率が低く、満了後に跳ね上がる設計が一般的です。解約予定より前倒しで満了を置くと安全度が上がります。
払込年齢は学費ピークより数年前に完了させると、想定外の出費にも対応しやすいです。
5. 出口戦略(解約・貸付・保有継続)
解約のほか、契約者貸付や一部解約の選択肢もあります。必要額とタイミングで最適な方法を選びます。
学費で使わなかった場合は、死亡保障を残して老後の備えに活用可能です。
注意ポイント
今の家計余力と老後資金計画を同時に点検。教育費を優先するあまり、老後準備が手薄にならないよう配分しましょう。
特徴比較|学資保険・終身保険・変額保険の使いどころ
それぞれの強みと弱みを把握すると、組み合わせの発想が生まれます。返戻率や使途の自由度、価格変動リスクを比較しましょう。
教育費に直結する観点から、代表的な3タイプを3列で整理しました。細目は各社の約款で確認を。
| 特徴 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|
| 学資保険 | 受取時期が固定で計画的 | 途中解約で返戻率が下がりやすい |
| 終身保険(低解約返戻金型) | 死亡保障+柔軟な受取 | 払込中は返戻率が低い |
| 変額保険 | 長期で資産形成と保障を両立 | 市場変動で元本割れリスク |
設計の実務|返戻率・払込期間・受取計画をどう整えるか
返戻率は「払込総額に対する解約返戻金の割合」です。払込満了直後と学費ピーク前後で、損益ラインを必ず確認しましょう。
受取は一括・分割・貸付の組み合わせで平準化。キャッシュフロー優先の設計が実務的です。
1. 払込満了年齢を学費ピーク前に
大学入学の2〜3年前に払込完了を置くと、安全余裕が生まれます。前倒しでの資金準備が肝要です。
途中解約の回避にも役立ち、返戻率の底打ちを防げます。
2. 受取方法の複線化(解約・貸付)
解約だけに頼らず、契約者貸付で一時資金を賄う手もあります。利息や返済条件を事前に確認しましょう。
貸付後に返済し、契約を温存すれば死亡保障も維持できます。
3. 返戻率が100%超の時点把握
返戻率が100%を超えるタイミングを必ず押さえます。そこまで保有する前提で計画を立てると損失回避に有効です。
途中解約の誘惑を避けるため、口座分離や積立自動化で意思決定を簡素化します。
4. 死亡保障額の適正化
収入・住宅ローン・教育費を基準に、必要補償額を算定します。過不足は保険料のムダや不足を招きます。
収入保障や定期保険の併用で、コストを抑えつつ必要額を確保しましょう。
5. 家計・老後資金との整合
教育費の積立が老後資金を圧迫しないよう、NISA等の積立と配分を調整します。バランスが長期安定の鍵です。
家計に余白を残すことで、突発支出にも対応できます。
見直しのコツ
毎年の家計決算で返戻率と目標達成度をチェック。進路変更や利率改定に合わせて微調整しましょう。
ケース別の向き不向き|こんな人は終身/学資/併用
目的が明確なら単独、複数の目的があるなら併用が合理的です。迷いを減らすため、代表的なパターンを示します。
判断は一律ではなく、家計や時間軸によって最適解が変わります。柔軟に選びましょう。
1. 終身保険が向くケース
死亡保障も欲しい、受取時期を柔軟にしたい、将来の返戻率上昇を狙いたい、といったニーズに合致します。
学費に使わなければ保有継続で老後資金のセーフティネットにもなります。
2. 学資保険が向くケース
受取時期が明確で、計画通りの受取を重視する家庭に適します。払込免除で教育資金の確実性も高められます。
ただし途中解約は不利になりやすく、柔軟性は限定的です。
3. 併用が向くケース
学費の核は学資で確保し、上乗せやリスク分散を終身で補う設計です。死亡保障も同時に強化できます。
家計の耐性に合わせ、保険料総額を管理しましょう。
教育資金は進学費用だけではない|習い事・体験学習も含めて考える
教育資金というと学費や入学金に目が向きがちですが、実際の家計では習い事や体験型学習への支出も無視できません。
特に小学生から中高生にかけては、興味関心を広げる学びが将来の進路選択に影響することもあります。
保険で教育資金を準備する際は、進学費用だけでなく、こうした継続的な教育支出も含めて全体像を整理することが重要です。
近年はオンライン学習など自宅で受講できる選択肢も増えており、家計負担を抑えつつ学びの幅を広げる方法として検討されるケースもあります。
例えば、デジタル分野の学習としてオンライン型のイラスト教室を体験できるサービスもあります。
まずは無料体験などを活用し、教育効果と家計バランスの両面から判断すると安心です。
FPに聞く!学資保険と終身保険のリアルな疑問

教育資金づくりの現場でよく問われるポイントを、FPがわかりやすく回答します。家計との両立や返戻率、変額保険の使い分けまで具体的に整理しました。
34歳・女性
終身保険を学資保険の代わりにする最大のメリットは何ですか?
スマホdeほけん
死亡保障と解約返戻金を同時に確保できる点です。家計の安全網を維持しつつ、教育資金の受取時期を柔軟に調整できるので、進路変更にも対応しやすくなります。
34歳・女性
返戻率はどのタイミングで見るべきでしょう?
スマホdeほけん
払込満了直後と学費ピーク前後の2点です。返戻率が100%を超える時点を把握し、その後に解約・一部解約・契約者貸付のいずれを使うか決めると、家計のキャッシュフローが安定します。
34歳・女性
学資保険と終身保険の併用はアリですか?
スマホdeほけん
有効です。核となる教育資金は学資で固定受取、上乗せや予備費は終身で柔軟に用意します。重複保障に注意しつつ、保険料総額が家計を圧迫しない範囲で配分しましょう。
34歳・女性
変額保険は教育資金に向いていますか?
スマホdeほけん
長期の資産形成には向きますが価格変動リスクがあります。受取までの年数が十分で、家計に余力がある場合に限定して活用し、元本確保が必要な時期は比率を下げるのが現実的です。
34歳・女性
解約の誘惑を避けるコツはありますか?
スマホdeほけん
「解約可能日」と「目標受取額」を先にカレンダー化し、口座を分けて積立を自動化します。急な出費は契約者貸付で一時対応し、計画外の全解約は避けるのが安全です。
34歳・女性
家計全体の配分はどう決めればいいですか?
スマホdeほけん
教育資金・老後資金・予備費の三層で考えます。保険料は年収の範囲内で固定費比率が上がり過ぎないよう管理し、NISA等の積立も併走させると長期の安定性が高まります。
よくある質問(FAQ)|契約・受取・見直し

最後に、迷いやすい論点をQ&Aで整理します。詳細は約款・注意喚起情報をご確認ください。
疑問が残る場合は見積書を用意し、専門家へ相談すると早道です。
Q1. 終身保険はいつ解約するのが得ですか?
A. 返戻率が100%を超えた後が目安です。学費ピークの前年など、必要時期に合わせて設定しましょう。焦って早期解約すると損失が出やすいです。
Q2. 途中で資金が必要になったら?
A. 契約者貸付で一時対応し、返済後に契約を維持する方法があります。利息や返済計画を事前に確認し、過度な借入は避けます。
Q3. 変額保険は教育資金に向きますか?
A. 長期での資産形成を狙える一方、市場変動で元本割れリスクがあります。時間分散と積立が前提となる点に留意してください。
Q4. 学資と終身のどちらが返戻率は高い?
A. 市場や料率改定で変動します。最新の見積比較が必須で、一律にどちらが上とは言い切れません。手数料や付帯条件も比較しましょう。
Q5. どのくらいの保険料が適正ですか?
A. 家計の固定費比率や老後資金の積立を考慮し、無理なく続けられる水準が適正です。年払い割引や払込年齢の調整も効果的です。
教育資金は進学費用だけではない|習い事・体験学習も含めて考える
学習塾や習い事の費用は、地域やサービス内容によって大きく異なります。
教育サービスの比較情報を参考に全体像を押さえておくことで、教育資金をどこに重点配分すべきか判断しやすくなります。
まとめ|教育資金は「設計力」で成果が変わる
終身保険は代替になり得ますが、解約時期・払込設計・返戻率の管理が成否を分けます。学資保険や変額保険との比較で、自分の家庭に合う形を選びましょう。
受取時期の明確化・返戻率100%超の把握・家計整合の三点を押さえれば、ムダなく教育資金を準備できます。
監修者からひとこと



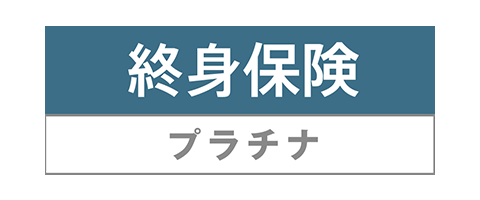
スマホdeほけん編集部監修者
ファイナンシャルプランナー
教育資金は「金額」と同じくらい「タイミング」が重要です。払込満了と受取の位置関係を設計し、解約の前提条件を数値で管理しましょう。途中の資金需要には契約者貸付も有効です。
また、資産形成を併走させるなら変額保険や積立を検討し、家計の余力を確保してください。過不足のない保障とコスト管理が、長期の安心につながります。