

スマホdeほけん編集部監修者
ファイナンシャルプランナー
保有資格
AFP・2級FP技能士
専門分野・得意分野
生命保険・社会保障・金融全般に精通。保険業界での実務経験をもとに、ユーザー目線で正確かつ中立的な情報発信を行っています。
「介護費用がどれだけかかるのか不安」「公的介護保険でどこまで賄えるの?」と悩む方は多いです。家計と老後資金に直結するテーマだからこそ、制度の範囲と自己負担の実態を正しく押さえることが重要です。
本記事では、公的介護保険のカバー範囲、自己負担になる費目、平均費用の目安と試算手順、貯蓄・投資・保険による具体的な備え方までをFP視点でわかりやすく解説します。
公的介護保険の基礎とカバー範囲を先に把握
介護保険は要支援・要介護の認定に応じて、訪問介護や通所介護などのサービス費用を原則1〜3割に抑える制度です。上限(支給限度額)内の利用で自己負担をコントロールできます。
一方で、居住費・食費・日用品・光熱費などは対象外となるため、制度だけでは埋められない費用ギャップを見込んでおく必要があります。
まずはチェック!カバー範囲の理解ポイント
1. 自己負担割合と支給限度額
自己負担は原則1割(所得により2〜3割)で、居宅サービスは要介護度ごとに月額の上限が決まります。上限超過分は全額自己負担です。
負担割合証や負担限度額認定証を確認し、毎月の利用計画をケアマネジャーとすり合わせましょう。
2. 対象サービスと非対象費用
訪問介護・訪問看護・通所介護などは対象ですが、居住費・食費・日用品・光熱費は原則対象外です。
施設入所時は「サービス費の自己負担+居住費+食費+日常生活費」の合計で考えるのが基本です。
3. 要介護度と上限額の関係
要介護度が高いほど上限額は大きくなりますが、使い切る前提で考える必要はありません。必要な支援に応じて柔軟に調整しましょう。
家族の就労状況や見守り体制により、外部サービスの比重は大きく異なります。
4. 高額介護サービス費の仕組み
同一月内の自己負担が一定額を超えると、超過分が払い戻される制度です。世帯単位で判定される点に注意してください。
申請や口座登録の不備で受給が遅れることがあるため、早めに手続きの流れを確認しましょう。
5. 自治体ごとの窓口と流れ
申請・認定・ケアプラン作成までは自治体と地域包括支援センターが起点です。まずは相談予約を入れましょう。
申請から認定まで一定の期間がかかるため、急ぎのケースは暫定ケアプランも視野に入れます。
注意ポイント
制度の対象と自己負担の境界を曖昧にしたまま計画すると、想定外の費用が膨らみます。認定結果が出る前から情報収集と必要書類の整理を進めましょう。
 保険料シミュレーション
保険料シミュレーション
自己負担になる費目とモデル費用イメージ
施設系・在宅系ともに、居住費や食費、日用品・介護用品、光熱費などの「暮らしの費用」は自己負担です。施設の種類や居室タイプで金額は大きく変動します。
家計の予実管理では、サービス費自己負担と暮らしの費用を分けて可視化すると誤差が減ります。
| 特徴 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|
| 在宅介護(居宅サービス) | 住み慣れた環境で継続可 | 家族の負担・見守りが必要 |
| 特養・老健など施設系 | 24時間体制で安心 | 居住費・食費が自己負担 |
| ユニット型個室 | プライバシーを確保 | 費用水準が上がりやすい |
自己負担の具体例を押さえる
居住費(家賃・室料)、食費、日用品・介護用品(おむつ・防水シーツ等)、光熱費、理美容代などが代表的です。
住宅改修は介護保険の支給対象(上限あり)ですが、超過分は自己負担になる点に注意しましょう。
費用管理のヒント
レシート・領収書を月次で集約し、サービス費と生活費を分けて記録。確定申告や払い戻し制度の下支えにも役立ちます。
平均費用とシミュレーション手順をステップ化
統計上、介護の月次費用は在宅・施設で大きく異なります。期間も平均で数年に及ぶため、初期費用+月次×期間の二層で試算します。
「誰が・どこで・どの程度」介護するのかを前提に、3パターン以上の家計シナリオを作成しましょう。
介護費用の試算フロー(家計シミュレーション)
1. 認定区分と上限額を確認
要支援・要介護の区分で使える上限が変わります。主治医意見書や心身状態の把握を丁寧に。
更新時期も費用に影響するため、更新スケジュールをカレンダー管理しましょう。
2. 在宅/施設の方針と優先度
在宅継続か施設入所かで費用構造が一変します。家族の就労や通院動線、夜間の見守り体制を加味します。
短期入所(ショートステイ)を緩衝材として活用する方法も検討しましょう。
3. 初期費用と月次費用の分離
住宅改修・ベッド・福祉用具は初期費用、居住費・食費・日用品は月次費用として分けて試算します。
初期費用の一部は給付対象になり得るため、制度適用後の純負担で見積もります。
4. 期間見込みと感度分析
平均期間に基づく試算に、±12か月の感度をかけて幅を持たせます。資金枯渇のリスクを低減できます。
医療費増や要介護度の変化も、代替シナリオに反映しましょう。
5. 軽減制度・税控除の反映
高額介護サービス費や医療費控除、自治体独自助成を反映し、実効負担を縮小します。
申請に必要な書類と期限を一覧化し、漏れなくキャッシュバックを受けましょう。
備えの三本柱:貯蓄・投資・保険を家計に最適配分
介護費用の準備は、流動性の高い貯蓄、非課税枠を活かす投資(NISA・iDeCo等)、現金給付が受けられる民間の介護保険を組み合わせます。
過不足の偏りを避けるため、「使う順番」と「取り崩しルール」を決めておくと安心です。
1. 貯蓄と予備費の設計
当面6〜12か月分の生活費+想定される介護初期費用を目安に現預金を確保します。突発支出に耐える体力が重要です。
家計簿アプリなどで月次キャッシュアウトを可視化し、取り崩し基準を共有しましょう。
2. 投資を活用した資産形成
つみたて投資で中長期の介護資金を育てます。非課税制度を優先し、分散・低コストを徹底しましょう。
リスク資産は老後資金と共通管理にし、年齢グライドによるリスク低減を設計します。
3. 民間保険の活用(介護・医療・変額保険)
介護保険の一時金・年金型や、医療・就業不能との組み合わせでカバー範囲を補完します。単身や遠距離介護は保険の有効性が高い傾向です。
長期の資産形成文脈では、変額保険で老後資金を積み立てつつ保障を確保する選択肢もあります。手数料とリスク特性の理解が前提です。
 保険料シミュレーション
保険料シミュレーション
在宅と施設で変わる費用管理のコツ
在宅は生活費の延長管理、施設は定額+追加費用の管理が基本です。どちらでも「見守りの外注」コストは想定以上になりがちです。
家族の介護時間と収入機会の損失も、家計の実コストとして算入します。
在宅介護:家計との両立
ヘルパー・デイサービス・ショートステイを組み合わせ、家族の介護負担を平準化します。夜間見守りの手当ても検討を。
用品はまとめ買いとレンタルを賢く使い分け、月次コストを抑制しましょう。
施設介護:選定と費用差
入所一時金の有無、月額費用、医療連携、看取り体制で費用と満足度が左右されます。必ず複数施設を比較しましょう。
入居後の追加費用(理美容・嗜好品・医療費)も、別枠で月額化して把握します。
見落としがちな点
家計の可処分所得が減る局面では、ケアプランを「やや控えめ」に再設計し、短期的に軽減制度と併用して凌ぐのも選択肢です。
申請・軽減・税控除を最大限に活用
高額介護サービス費、負担限度額認定、医療費控除、障害者控除など、活用可能な制度は多岐にわたります。担当窓口と役割分担を整理しましょう。
証拠書類と申請期限の管理は、家族内のタスク管理表で共有すると漏れを防げます。
申請手順の基本
必要書類の準備→窓口確認→申請→審査→給付の流れです。並行してケアプランの見直しを行い、実負担の最適化を図ります。
オンライン申請や郵送対応の可否も事前に確認しましょう。
税控除・助成の把握
医療費控除は介護関連の一定費目が対象になる場合があります。領収書の保管と明細化が鍵です。
自治体独自の助成・貸与は、条件や枠に限りがあるため早めの情報収集が有効です。
Q&A:介護費用と備えのよくある疑問

Q1. 公的介護保険だけで費用は足りますか?
A. 多くのケースで不足が生じます。居住費・食費・日用品などの自己負担があるため、貯蓄・投資・保険の併用が現実的です。家計の状況に合わせて配分を決めましょう。
Q2. 在宅と施設、どちらが安いですか?
A. 一般に在宅の月額は抑えやすい一方、家族の負担や見守りコストが増えます。施設は安心度が高い反面、居住費・食費が上乗せされます。優先度で選びましょう。
Q3. いつから準備を始めればよい?
A. 40代から制度理解と試算、50代で具体的な資金計画が目安です。非課税枠を使った積立は早いほど有利です。
Q4. 保険は何を選べばいい?
A. 介護一時金・年金型、医療・就業不能の組み合わせが基本です。長期の資産形成を兼ねるなら変額保険も検討対象ですが、手数料とリスクを理解しましょう。
Q5. 軽減制度はどうすれば使える?
A. 条件確認のうえ申請が必要です。ケアマネと自治体窓口で要件を確認し、月次で実負担額を点検して適用漏れを防ぎましょう。
 保険料シミュレーション
保険料シミュレーション
まとめ
介護費用は、公的介護保険で抑えられる部分と自己負担が生じる部分に分かれます。家計と老後資金を守るには、制度理解に加えて、初期費用+月次費用×期間の試算と軽減制度の活用が不可欠です。貯蓄・投資(NISA等)・保険を組み合わせ、在宅と施設のシナリオ別にキャッシュフローを用意しておきましょう。
監修者からひとこと
外資系保険会社での営業経験を活かし、現在はお金に関するコラムの執筆を行っています。保険や家計、資産形成など、日々の暮らしに役立つ情報をわかりやすく伝えることを大切にしています。AFPおよび2級ファイナンシャル・プランニング技能士の資格を持ち、実務経験と専門知識の両面から、信頼性の高い情報提供を心がけています。
保有資格
AFP・2級FP技能士
専門分野・得意分野
生命保険・社会保障・金融全般に精通。保険業界での実務経験をもとに、ユーザー目線で正確かつ中立的な情報発信を行っています。



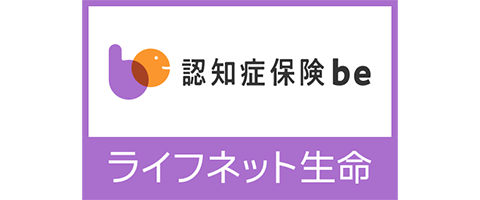

スマホdeほけん編集部監修者
ファイナンシャルプランナー
介護の備えは「制度でどこまで」「家計でどう埋めるか」を同時に設計することが重要です。要介護度や家族の就労状況で最適解は変わるため、在宅・施設・短期入所のミックスや、軽減制度・税控除の適用可否まで一気通貫で確認しましょう。さらに、貯蓄は流動性、投資は非課税枠、保険は現金給付と役割を分担させ、取り崩しの順番とルールを家族で共有することが実装面の鍵です。計画は定期点検を前提に、状況変化に合わせてアップデートしてください。